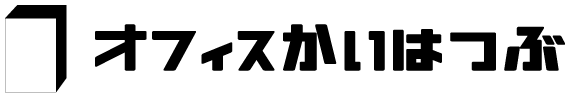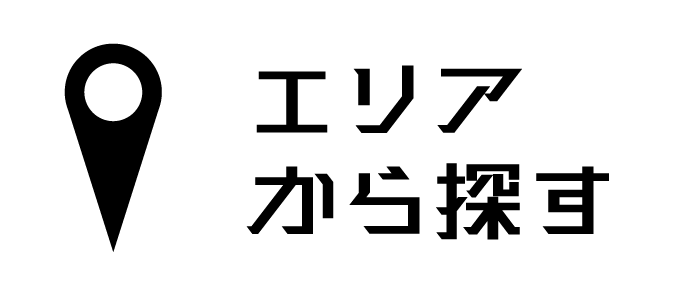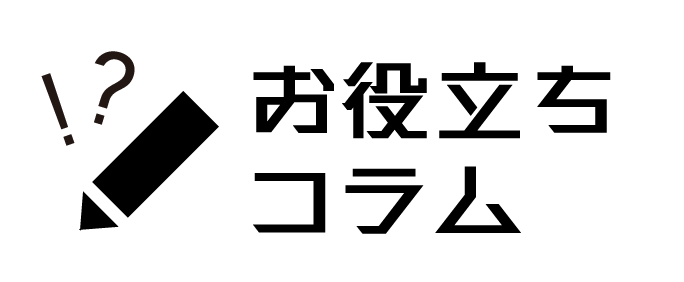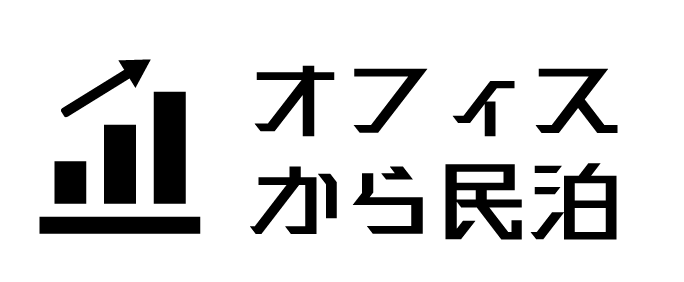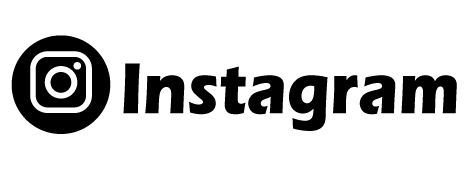中央区のお祭り一覧と由来まとめ
日本橋・銀座・築地・月島など多彩な顔をもつ中央区は、江戸から続く商都と水都の歴史が息づく祭礼の宝庫です。ここでは代表的なお祭りと「なぜ始まったのか(由来)」を、エリア別にわかりやすく紹介します。※開催日は年により変わるため、最新情報は公式発表をご確認ください。
主なお祭り(クイック一覧)
- 築地・波除稲荷神社「つきじ獅子祭」(6月)
- 日本橋恵比寿講「べったら市」(10月19・20日)
- 佃・住吉神社例祭(佃祭/8月・3年に一度本祭で船渡御)
- 日本橋蛎殻町・水天宮 例大祭(5月5日)
- 築地本願寺 納涼盆踊り(夏・4日間)
- 人形町「甘酒横丁 桜まつり」(春)/SAKURA FES NIHONBASHI(春)
- 小網神社「どぶろく祭」(11月28日)
- 日本橋・京橋まつり(10月)
- 新春「日本橋七福神めぐり」(元日〜松の内)
各祭りの見どころと由来
築地・波除稲荷神社「つきじ獅子祭」
江戸初期、築地の埋立て工事の難航を鎮めたご神徳に感謝して、巨大な獅子頭・龍・虎を奉納し担いだのが始まりとされます。以後、「災難を除き波を乗り切る」波除さまとして崇敬され、今も勇壮な獅子頭が町を練り歩きます。
日本橋恵比寿講「べったら市」
宝田恵比寿神社の門前で、10/20の恵比寿講に供える品を前日19日に買い求める市が起源。浅漬け大根「べったら漬」が評判となり名物化。大提灯と提灯の海に包まれる夜の日本橋本町は、江戸の商い文化を今に伝えます。
佃・住吉神社例祭(通称:佃祭)
徳川家康の関東入府に縁ある摂津国・佃(大阪)からの漁師らが分霊を奉じ創建したのが佃の住吉神社。毎年8月に例祭、3年に一度の本祭では八角神輿の宮出しや、神輿を船で巡らす勇壮な「船渡御」が行われ、水都・中央区らしさ満点です。
日本橋蛎殻町・水天宮 例大祭
安産・子授けで知られる水天宮の例大祭は毎年5月5日。境内では神事が厳かに営まれ、周辺は露店で賑わいます。江戸町人の信仰とともに歩んだ、日本橋人形町エリアの春の風物詩です。
築地本願寺 納涼盆踊り
築地本願寺の境内にやぐらが組まれ、連夜の輪踊りが広がる人気行事。「日本一おいしい盆踊り」とも呼ばれ、築地場外の名店屋台がずらり。お盆の供養に由来する盆踊り本来の所作や法要も大切に継承されています。
人形町「甘酒横丁 桜まつり」/SAKURA FES NIHONBASHI
春の人形町では甘酒の無料振る舞いや福引などで賑わう「甘酒横丁 桜まつり」を開催。通り名は明治期、尾張屋という甘酒屋に由来します。日本橋一帯では「SAKURA FES NIHONBASHI」が開かれ、江戸桜通りのライトアップや屋台・スイーツ企画で街全体が桜色に染まります。
小網神社「どぶろく祭」
新嘗祭に由来し、毎年11月28日に行われる行事。五穀豊穣と息災を祈って神前に供えたどぶろくが参拝者に振る舞われます。日本橋の福の神として親しまれる古社らしい、秋の実りを寿ぐ祭りです。
日本橋・京橋まつり(大江戸活粋パレード)
昭和47年に国道整備記念のパレードとして始まった都市型の祭り。現在は日本各地の郷土芸能や踊りが中央通りに集い、地域と来街者が一体になる秋のハイライトです。
新春「日本橋七福神めぐり」
元日から松の内にかけ、日本橋の7(または8)社を巡拝する開運行事。室町期に広まった七福神信仰を背景に、人形町〜日本橋界隈の小社をつなぐ“まち歩きの巡礼”として定着。短距離で回れる手軽さも魅力です。
ワンポイント:中央区の祭礼は、商家の講(恵比寿講など)や、埋立・海上交通の安全を願う信仰、寺社縁起(安産祈願・先祖供養)など、商都と水辺に根を張った由来が多いのが特徴です。